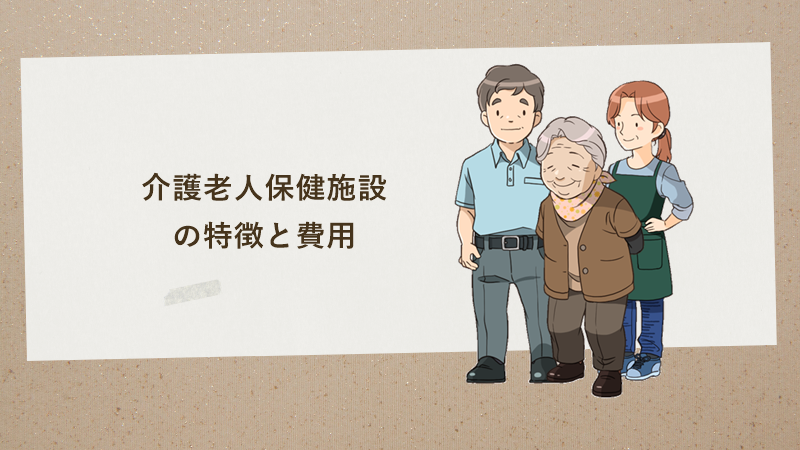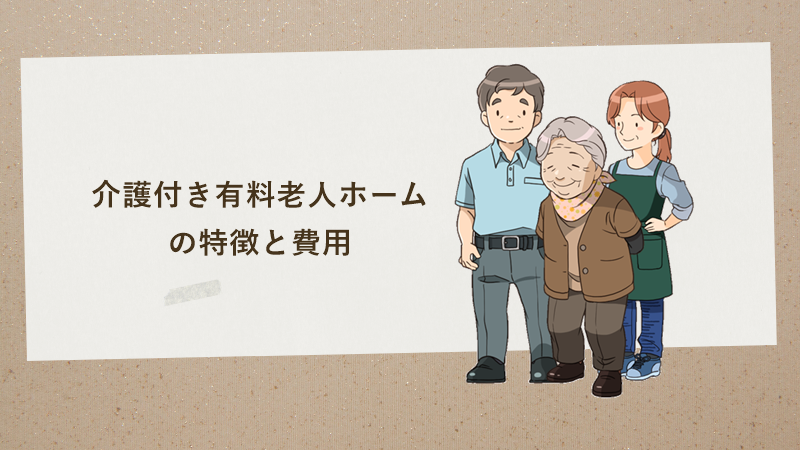「終活」お葬式のスタイル を比較する!プランと費用から見る人気ベスト3!
更新日

気になりますよね… お金のこと。 お葬式は、人生の最期に支出される費用。大切なご家族のためにも、事前の準備ではしっかりとお葬式の費用を把握し、万全な終活を心掛けていただきたいと思います。 しかしながら、お葬式の費用とは、分かりにくいもの。 近年では様々なスタイルの葬儀が行われるようになり、価格プランは多様化。プランの名称や内容は葬儀社によって異なるうえ、いざ見積取得を行っても、お葬式のイメージが湧かず、費用を把握しにくいという言葉をよく耳にします。 また、最近ではコロナウイルスの流行もあり、お葬式を検討される方にとっては、どのようなお葬式選びが良いのか、判断が難しいことと思います。 そこで、ここでは初めて終活を行う方でも、簡単にお葬式スタイルの内容と費用が把握できるように解説! 既に葬儀社から見積取得を行っている方も、価格プランがどのお葬式スタイルに該当するかを確認することで、お葬式のイメージが湧き、費用相場との比較が行えるので、どうぞ参考になさってください。 更に、今だから気にせずにはいられない『コロナ感染防止対策』の情報も掲載。コロナ禍でも安心の葬儀社選びのポイントを掲載しています。 便利な最新情報で、簡単終活!理想にピッタリのお葬式スタイル選びで、費用の把握と葬儀社比較にお役立てください。 【簡単終活】最新版お葬式スタイル別の費用相場とは? 祭壇や僧侶へのお布施や料理など記載は、一般的なお葬式内容と費用相場です。参列者の人数のほか、斎場使用料・祭壇ランク・料理ランク・お布施の金額などによって費用は異なりますので、ご注意ください。 なお、葬儀社選びにあたっては、気になるお葬式スタイルについて、品目と費用を把握するために見積取得を行います。少なくとも2~3社の見積比較を行い、品目の過不足と、品目ごとの費用を比較しましょう。プランによっては、品目が含まれていない場合などがありますが、多くの葬儀社ではプラン内容の変更が可能です。 満足度を向上するためには、品目ごとに質をランクアップしたり、不要な品目を削減したりすることで、より理想的なお葬式プランに仕上がります。難しいように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、日常生活に置き換えると、「欲しいものを得るために、無駄遣いをやめる」という作業ですので、是非とも取り組んでいただくことをおすすめします。 以降紹介する金額はあ